編集手帳:長安が月光満ちる
フランスの画家レミ・エヨンは、「すべての芸術は制約から生まれ、自由によって死ぬ」という言葉を言ったことがある。文学の方面では、似たようなことを、賈平凹氏も言ったし、木心氏も言った。——もっとわかりやすく言うと「规矩無ければ、方円ならん」と。小説のジャンルでは、その制約というのが風格である。多くの作家は作品を持っているが、必ずしも自分の風格を持っていない。

『聞道長安』を初めて読んだとき、これはいったいどういう風な作品であろうと、ずっと考えていた。私と同じようにまずカフカを思い浮かべ、『変身』や『城』を思い浮かべる読者もいるかもしれない。その時代、カフカは世界文学の新技法、新境地を開拓し、現代に至るまで愛され続けている。芸術の革新がいかに魅力的であるかがわかる。象徴主義、表現主義、ダダイズム、幻的リアリズム……。作品を完成させた作家には、自分の作品を説明する義務がない。解釈は評論家と読者の仕事だ。
『聞道長安』は一部の極めて探索的な小説で、その実験性は、はるかにその芸術性といわゆる社会の意義を超えて、ちょっと比較してみれば:『変身』の手法は堅苦しくて謹直、『聞道長安』の手法は飛躍式で柔軟に変わりやすい。カフカの文体は陰気な色合いを帯びていて、悲観的な雰囲気が漂っている。蕭跡さんは世事に通じた逍遥で、笑ったり怒鳴ったりして既成なルールを無視する。カフカの荒唐無稽は人為的で、その時代のメタファーであり象徴だ。蕭跡の荒唐無稽は、時代はすでに不条理に満ちていて、人は金と物質の社会でとうに仕方なく異質化されているということだ。
主人公の「私」は私であるが、唯一の私ではあるまい。趣縁斎の主人蕭跡であっても、李白や蘇東坡のような名士であっても、白髭の老人であっても、棺に入ったミイラであっても、犬であっても……読者は「荘周夢蝶」や「三体」、「インセプション」といったSFに慣れていくと、『聞道長安』の「四次元」理論をバリアフリーで受け入れることができる。四次元の空間では、時間は存在せず、主人公の私は目を覚ましながら夢を見て、唐の天宝年間から西暦2050年まで、仮想の時間の空間に自分を自由に行き来させ、置き換える。時間は質感のある「平行な」光になっている。
「私の頭の隙間から明るい光が出てきました。その光の帯には羽という字が浮かんでいました」。著者の筆先からは垓下の戦いで項羽が剣を抜いて自刎する場面と、麦城に敗走した関羽が首を切る場面が出てくる。
私と名乗った白ひげの老人は、私と議論を交わした後、少し離れた産婦人科に光となって飛び込んでいき、お産をしている妊婦のそばで消えていくと、赤ちゃんの高らかな泣き声が聞こえてきた。
一言で言えば、『聞道長安』は一つの夢で、そしてはっきりとした夢である。小説の終わりの中で兄の海文が言うように「一晩で何千年を走った。」夢の中には王公将相もいれば、英雄美人もいれば、妖怪もいれば、猫もいれば犬もいる。しかし、『聞道長安』は現代版の唐伝奇でもない、SF版の『聊斎志異』でもない。これは妙なリアリズム小説だ。
「私」が李白になったとき、「私は五斗米のために腰を折らなければならない、あなたと遊んであげても、あなたには決して馬鹿にされない」という態度を持つ。
「私」が蘇東坡になったとき、友人の仏印に「私は誰ですか?」と聞き、仏印が「あなたは誰にでもいいよ」と答えると、即座に悟った。
「私」が浮く魂と信仰について議論していると、魂は「何を信じようが、どうでもいい」と言った。
自分が犬であることを忘れた私に、猫は「あなたは一人前の男が尊厳のない犬のように生きていいですか?」
……
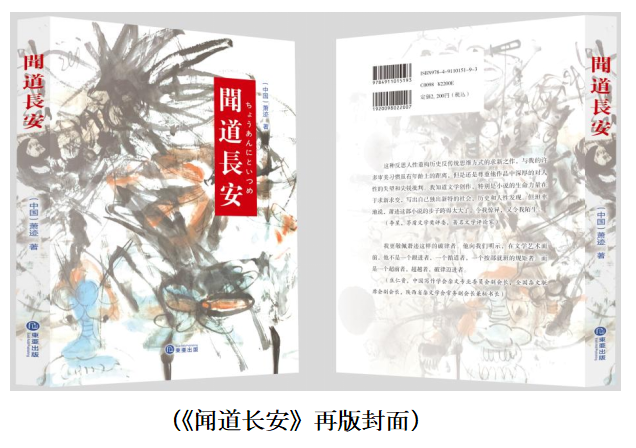
文章は千古の大事で,1つの人間性を抜きにすることはできない。小説の中の人物のセリフはすべて「夢は現実に照らして」で、万変は人情、飲食の男女を離れないので、作者は自由に時間の中で行き来することができて、役の上で転換し、時空の交錯に任せても読者はでたらめと唐突さを感じない。
言語でさえも現代の流行色だ。MM、卧槽、SB観客、TMD……さらに西安の方言にもあちらこちら使っている……これらは小説の特色と言える。もう一つの特色は意識流のタッチでやることが多いことだ。例えば風景の描写、長安東西市であれ、興慶宮であれ、華清池であれ、風景描写はほとんど省略した、なぜかというと、映像ができるように風景は文字で述べる必要がない。
『聞道長安』を初めて読んだ時、読者たちは夢枕獏の小説『大唐鬼宴』(後に映画化された『大唐妖猫伝』)を思い出しやすい、どちらも奇妙な「主人公猫」が登場する。夢枕獏が書いた猫は玄宗が好きなペット御猫で、蕭跡が描いた猫は、楊玉環の代わりに自殺した女官の芍薬で、死後は猫に化けて犬になった「私」に夢中になって付き添う。この犬になった私は、蕭跡であり李白でもある。小説の最初の6章は引き立ての存在で、我々は交響曲の前奏曲と理解してよい、第7章「私は犬になった」から、小説の構造が見える輪郭を探して、著者は答えを探して、つまり「私」はどのように人間から犬になって、私はどのようにして「私」を取り戻す、つまり、人間としての尊厳を取り戻す。──それこそがこの小説の「核」なんだ。物欲横流の今、尊厳と自尊はどんなに赘沢なものになって、女の人の素顔のようにめったに見られない。
でも、一つひとつの章が続いているわけではないから、迂回して、スネークライン。登場人物もだらしなく、夢の映像に色がないように、小説の中の人物には性格が隠されている。あるいは、主人公以外の登場人物は意図的に作られたものではない。これらのまやかしや鬼は、みんな「成り行き」で、都合の良い格安の労働力だ。
では、この小説の意味は何であろうか。——小説に意味は必要だか。人生に意味などないのに、いわんや芸術をや、である。ここ数年、読者はそういう上から目線の説教的な作家や作品に飽きてきた。趣味的、面白い作品はなかなか出にくい。読むことは楽しむことだ、読む価値があることがその作品のすべてだ。
四次元は本当に存在するのか?私から見れば、それは偽の概念であり、信じられない、自洽性のない想像だ。しかし、人生や運命には解釈が必要であり、より多くの視点が必要であり、ファンタジーやSF、怪力乱神の小説は古来から絶えぬ。豊臣秀吉の絶命書では、自分の人生を「夢の中の夢」と表現して、世に多くの気づきや啓発を与えている。
「聞道長安似弈棋」、長い十三朝代の古都は、それは中国の歴史文化の上での存在感が強すぎて、読者は『聞道長安』の期待には作者に何か新しい遊びをさせなければならない。幸い、最初から最後まで一気に読める本なので、十分気持ちいい。題材から形式まで趣向をこらしていて、目も耳も一新する。
昔も今も長安を書く詩は数え切れないほどあるが、私にはあえて李白の『長安夜』に心が惹かれる、月光満ちる長安の夜には:
長安一片月、万戸搗衣音。 (長安 一片の月 万戸 衣をうつの聲)
何日平胡虜、良人罷遠征。 (何れの日か 胡虜を平らげ 良人 遠征を罷めん)

(和訳:小山長州 東亜出版編集長、文学翻訳者)

